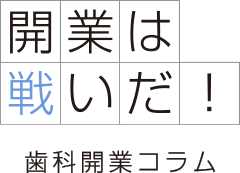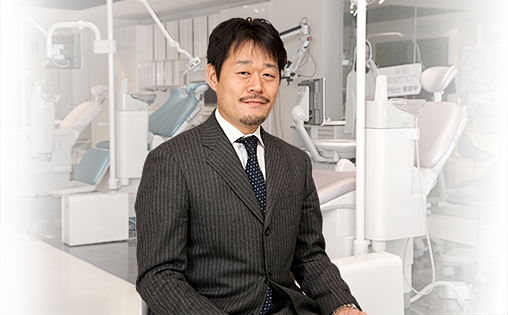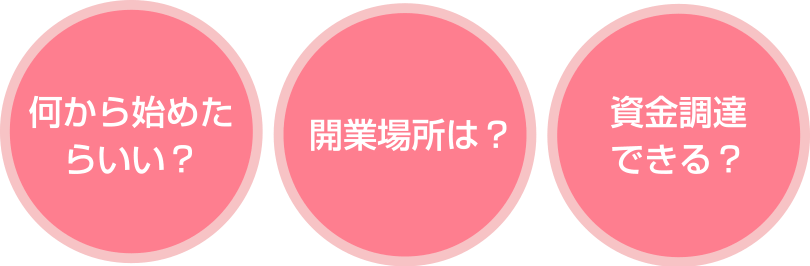安心して長期で使える節税制度の検討を
今回は、年度始めということもありますので皆さんが気になる「開業後の節税」についてお話します。では早速、具体的な対策の一例を見ていきましょう。
① 歯科医師国民年金基金に加入する
歯科医師国民年金基金は国民年金の上乗せになる公的な個人年金で、65歳から受け取ることができる終身年金です。掛金は全額が社会保険料控除になり、所得税や住民税が安くなります。月々の掛金の上限は68,000円です。
② iDeCo(イデコ)に加入する
iDeCoは自分が拠出した掛金を運用して資産形成する年金制度です。「小規模企業共済等掛金控除」が適応できるため、経費と同じ効果があります。①で挙げた国民年金基金と一緒に加入できますが、その場合は掛金の合計が68,000円を超えない範囲での併用となります。
税制メリットがある制度ではありますが、こちらは運用次第ではリスクも。歯科医師国民年金基金とiDeCoどちらか悩むようでしたら、元金が確実な歯科医師国民年金基金をお奨めします。
③ 小規模企業共済に加入する
小規模企業共済とは小規模経営者や個人事業主のための退職金制度です。掛金は1,000円から上限70,000円まで自由に設定が可能。こちらも掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除ができるので経費と同じ効果があります。
例えば、積立期間が20年以上で65歳以上まで加入すると掛金総額を上回る金額を受け取ることができますが、20年未満で解約すると元本割れのリスクが生じます。資金繰りが大変な時期は、解約するよりも掛金を低く見直して負担を抑えるのがベター!小規模企業共済は個人事業の歯科医師は加入できますが、事業主が医療法人を設立すると加入できなくなるので注意が必要です。
国民年金基金・小規模企業共済を優先
節税対策に有効な制度をいくつかご紹介しました。いずれも比較的加入しやすいものを挙げてみましたが、開業された先生の中には国民年金基金や小規模企業共済に加入せず、高額な生命保険に入っておられるケースも…!
この場合、生命保険料控除は所得控除できる額が50,000円と少ないため、全額を控除できる国民年金基金と小規模企業共済に加入してから生命保険に加入するよう優先順位を決めておくのがポイントです。
上で紹介した3つの制度は国が認めた合法的な節税方法です。安心して長期で加入できる制度なので、老後の備えも視野に入れながら無理なく節税をしていきましょう!
>>開業資金関連など、森川会計へのお問い合わせは
歯科開業・歯科経営サポート「税理士法人 森川会計事務所」
◆【新セミナー動画】森川先生が講師を務めるセミナー版「開業は戦いだ!」の新しい動画がアーカイブに追加
近い将来、開業を目指す勤務医の先生に向けた耳より情報満載!コラムと併せてぜひご視聴ください。